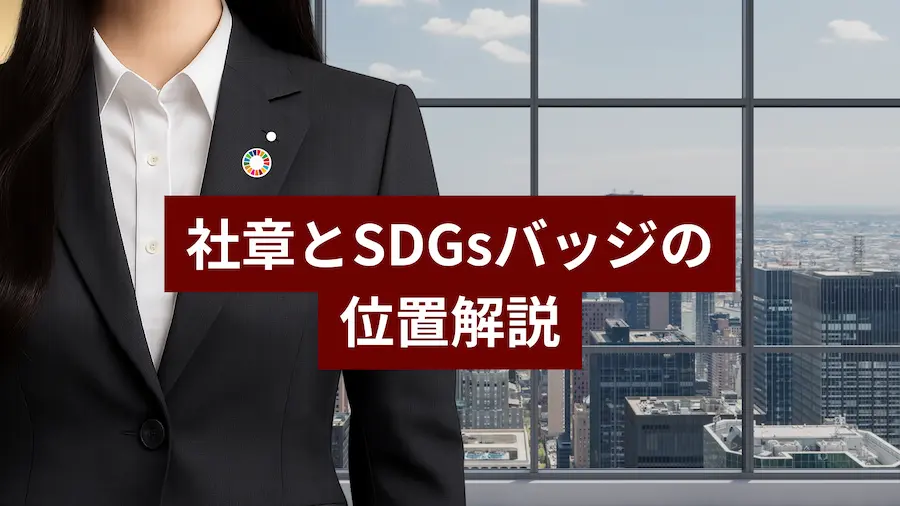
ビジネスの現場では、社章やSDGsバッジなどの徽章(きしょう)を身に着ける機会が増えています。
とくにSDGsの認知度が高まる中で、「社章とSDGsバッジ、どちらを優先して付けるべきか」「そもそも両方つけてよいのか」「並べ方や位置にマナーはあるのか」といった声が多く聞かれるようになりました。
これらの疑問の背後には、「失礼な印象を与えたくない」「社外でも恥ずかしくない装いをしたい」といったビジネスパーソンとしての不安が潜んでいます。
バッジの位置ひとつで、相手に与える印象や信頼感は大きく変わるため、見落とせないポイントです。
本記事では、社章とSDGsバッジを両方つける際の正しい位置関係や優先順位を、マナー・TPO・服装ごとの実例を交えて丁寧に解説します。
また、クールビズや女性の服装への応用、留め具選びやNG例など、実務でそのまま使える内容に絞ってご紹介します。
この記事を読めば、以下のような実践的な判断ができるようになります。
- 社章とSDGsバッジ、正しい位置と優先順位がすぐに分かる
- スーツ、シャツ、女性服装など、あらゆる服装パターンで迷わない
- TPOや社内ルールに沿って、自信を持って装着判断ができる
- NG例や留め具の選び方など、細かな運用トラブルも防げる
初めての方でもすぐに理解できるよう【図解】を交えて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
本記事でご紹介する内容はあくまで一例であり、必ずしもすべての状況に当てはまるとは限りません。実際の導入にあたっては、小規模なテストや調査を行い、自社の環境や目的に適しているかを確認いただくことを強くおすすめします。
なお、社章についての全体像については、以下のガイドで網羅的に解説しています。まずはこちらからご覧いただくと、より理解が深まります。
→ 社章とは?意味・マナー・付け方・紛失対応・作成方法までガイド

監修・執筆:誉花
誉花は、「{しるし × ものづくり} × {アカデミック × マーケティング}=価値あるしるし」をコンセプトに活動しています。社章やトロフィー、表彰制度が持つ本質的な価値を科学的かつ実務的な視点から探求・整理し、再現性の可能性がある知見として発信しています。私たちは、現場での経験と調査・理論を掛け合わせ、人と組織の中に眠る「誉れ」が花開くための情報を提供しています。
この記事免責事項
本記事では、SDGs(持続可能な開発目標)に関する啓発・普及を目的とし、国連が定めた「SDGsロゴおよび17のアイコン使用ガイドライン(2019年8月日本語版)」に基づき、正しい使用方法を遵守したうえでロゴ・アイコン等を掲載しております。
使用に際しては、以下の条件を満たすよう細心の注意を払っております。
- 情報提供を主目的とし、商用目的ではないこと
- ロゴ・アイコンの色・形状・比率の改変を一切行っていないこと
- ガイドラインに沿って「背景処理(ロゴ〈カラー版〉は白またはライトグレー/白黒版は黒。アイコンは公式規定に準拠)」を行っていること
- ロゴ使用により国連による承認・支援・提携を示唆しない表現としていること
- 関連出典・参考リンクを明示していること
- 他ロゴとの統合・組み合わせを行わないこと
- SDGs図像と自社ロゴを同一面で横並び等の近接併置にする場合は、その近傍に「[社名]は持続可能な開発目標(SDGs)を支持します」を併記すること
- ガイドラインの更新有無を定期的に確認すること
- SDGs図像の使用は原則2030年12月31日まで(刊行物等は例外あり)
本記事におけるSDGs関連素材の使用は、国際連合の承認や支持を意味するものではありません。
万一、本記事の内容または使用方法に問題や不備がございましたら、速やかに修正・削除等の対応をいたしますので、恐れ入りますがご連絡ください。
【出典】
→国連公式 SDGs サイト(英語)
→SDGsロゴと17のアイコン使用ガイドライン(PDF/日本語)
目次
基本原則:なぜ社章が優先されるのか
結論から申し上げると、社章はSDGsバッジよりも上に配置するのがビジネスマナーとして基本です。これは見た目の問題だけでなく、それぞれの徽章が持つ意味の違いに基づいています。
優先順位の理由は「象徴性と立場の違い」にある
社章とSDGsバッジは、どちらも胸元に付ける小さなアイテムですが、それぞれが表す意味は異なります。配置の優先順位を決めるには、まずそれぞれの役割を理解することが重要です。
- 社章:企業への帰属意識と代表性を示す徽章。
- 「私はこの会社の一員であり、責任ある立場でここにいる」というメッセージを含みます。
- 来客対応や式典など、会社を代表する場面では最も重要な象徴になります。 - SDGsバッジ:持続可能な社会の実現に向けた賛同の意思表示。
- 国際的な目標への共感を示す個人または組織の姿勢を表します。
- 公共性は高いですが、あくまで任意であり、個人の主張に近い側面もあります。
このように、社章は組織を背負っていることを示す「公式な記章」であり、SDGsバッジは任意参加の理念的アピールです。したがって、見た目だけでなく意味の優先順位としても「社章が上、SDGsバッジが下」とするのが自然なマナーとなります。
配置ルールの原則
| 項目 | 社章 | SDGsバッジ |
|---|---|---|
| 象徴するもの | 会社・組織・所属 | 国際目標・理念・賛同 |
| 装着の義務 | 就業規則で定められることが多い | 任意(強制力なし) |
| 優先順位 | 上(主役) | 下(補完的) |
| 装着目的 | 所属と責任の明示 | 意識・姿勢の表明 |
| 推奨位置 | 左襟フラワーホールまたは相当位置 | 社章の直下(上下並び) |
このように、それぞれの徽章の性質と目的を整理すると、社章が“主”、SDGsバッジが“従”という位置関係が自然であることが見えてきます。
補足:SDGsバッジの方が目立つ場合の配慮
SDGsバッジはカラフルな色合いが特徴的であるため、視覚的に強調されやすい傾向があります。そのため、配置によってはSDGsバッジだけが目立ち、社章の存在感が弱まってしまうこともあります。
このような場合には、以下のような工夫を検討するとよいでしょう。
- SDGsバッジのサイズをやや小さめにする
- 社章との間隔を広げすぎない(5〜10mm程度)
- 社章をより目立つ材質・デザインにする(艶消し/鏡面など)
また、会社によっては「SDGsバッジの装着を推奨しない」「社章のみとする」などの明確な方針を持っているケースもあります。最終的には社内規定を確認することが第一であり、この記事はあくまで一般的なマナーとしてご活用ください。
【図解】スーツ・ジャケット着用時の正しい位置

スーツやジャケットを着用するビジネスシーンでは、社章とSDGsバッジの配置に最も配慮が求められます。基本のルールは「左襟に上下で並べて配置」「社章が上、SDGsバッジが下」です。視認性・印象・マナーの観点から、この順序を守ることが望ましいとされています。
フラワーホールあり:社章=ホール、SDGs=直下
フラワーホールがあるスーツやジャケットの場合、社章はフラワーホールに直接装着し、そのすぐ下にSDGsバッジを並べて配置するのが最も正式とされます。
- 社章:左襟のフラワーホール(縦の切り込み)にピン留め
- SDGsバッジ:社章の直下、垂直方向に少し間隔を空けて配置
- 上下間隔の目安:5〜10mm(見栄えのための参考。社内規定があればそちらを優先)
この配置は、社章の「組織を代表する記章」としての象徴性を最上位に置きつつ、SDGsバッジの理念的な意味もスマートに補完する形になります。
※【図解指示】:フラワーホール位置に社章、そこから5〜10mm下にSDGsバッジを配置したシンプルな横顔図。視線誘導の軌道も薄線で補足。
フラワーホールなし:襟角からの相当位置→その直下にSDGs
フラワーホールが付いていないジャケットやスーツでも、同じ原則に従います。フラワーホールに相当する位置を襟の内側角から計測して社章を配置し、その直下にSDGsバッジを並べます。
- 社章の目安位置:
- 襟の外角(ラペルポイント)から内側約30mm・上方向約15mmを相当位置の目安(見栄えの参考。社内規定優先)
- SDGsバッジ:社章の真下、5〜10mmの間隔で配置
- 注意点:襟の傾斜や幅により、上下の配置が斜めにならないよう垂直を保つ
この配置は、フラワーホールがなくても社章を正しい位置に装着できるようにする実務的対応策です。フラワーホールのあるジャケットと見劣りしないスマートな印象を与えられます。
※【図解指示】:襟角からの測定ガイド線+社章→SDGsの順で縦配置された例図。距離と角度の参考表示付き。
【これはNG】印象を落とす3つの配置と直し方
以下のような配置は、視認性やビジネスマナーの観点から避けるべき典型的NG例とされます。違和感を与える原因を理解し、正しい付け方に直すことが重要です。
NG例と改善策
| NGパターン | 原因 | 改善ポイント |
|---|---|---|
| 左右バラバラ(社章:左、SDGs:右) | 視線が分散し、印象が雑になる | 左胸に縦に並べるのが基本 |
| 位置が低すぎる | 襟元の基準位置が無視され、だらしない印象に | 襟角〜30mm内・15mm上が目安 |
| 多点付け(3つ以上) | 情報過多で印象が混乱しやすい | 最大2点までに絞り、優先度で選定 |
これらの誤った配置は、「マナーを知らない人」として見られるリスクがあります。特に新入社員や対外対応のある職種では注意が必要です。あくまでも“読み取りやすさ”と“清潔感”を意識して、シンプルに整えることが肝要です。
※【図解指示】:NG例3パターン(バラバラ配置・低位置・多点)と、それぞれのBefore→After改善図を1枚に整理
クールビズ(シャツ・ポロ)の運用
クールビズ期間中は、ジャケットを着用しないスタイルが一般化しており、社章やSDGsバッジの取り扱いにも柔軟性が求められます。この時期においては、「付けない選択」が基本であり、無理に装着する必要はありません。
基本方針:クールビズでは“付けなくても問題なし”(多くの企業運用で一般的/襟やポケットがない衣類は非装着を前提に判断)
多くの企業において、クールビズ期間中に社章やバッジの着用を義務づけるケースは少数派です。理由は以下の通りです。
- 襟元が省略されることで、バッジの取り付け位置が定まりにくい
- 通気性や快適性を重視する場面では、装着自体が負担や違和感につながる
- 社章や社員証などの識別は、必ずしも胸元にバッジを付けることでのみ達成されるものではない
そのため、基本方針としては「クールビズ時は付けなくてもマナー違反にはならない」という立場が一般的です。
付ける場合の基準位置:服の形状に合わせた配置が必要
一方で、来客対応や公式な社外対応がある日など、状況によっては「バッジを着けたい/着けるべき」ケースも想定されます。その際は以下の基準位置が推奨されます。
シャツの場合(ポケットあり)
- 原則は上下(上=社章/下=SDGs)。水平に並べる場合は左=社章/右=SDGs
- 社章が上、SDGsが下の順序を守りつつ、バランスよく配置
- 間隔は5〜10mmを目安とし、ポケット口に接触しないよう配慮する
ポロシャツの場合(ポケットなし)
- 身頃左上(前立ての左側・肩線から下10〜15cm付近)を目安に
- 柔らかい素材では傾きや垂れ下がりが起きやすいため、小さく軽いバッジが望ましい
- マグネット留めなどで服地を傷めず固定する方法が推奨される
※【図解指示】:シャツにバッジをつけた場合と、ポロシャツにマグネット式で装着した例を並列表示。基準線と垂直軸の注釈あり。
経験:「社員証ホルダーに社章を固定した例(※セキュリティ規程・落下リスクに留意)」
ご経験において、ジャケットを着用しない場面で社章をつける必要があった際、社員証ホルダー(カードフォルダー)に社章を留めて対応した実例がございます。(※所属組織のセキュリティ規程に従うこと)これは以下のような実務的な利点があります。
- 衣服に穴を開ける必要がない
- 名札と社章が同じ場所で視認できる
- 着脱が容易で、TPOに応じて即対応が可能
このような臨時的な工夫は、「装着したいが服装上の制約がある」場面において有効な対処法といえます。
ただし、社員証ケースの材質や厚みにより固定が甘くなることもあるため、恒常運用には不向きであることも併記しておく必要があります。
無理に着ける必要はなく、公式場面のみ臨機運用すべき
結論として、クールビズ時におけるバッジ装着は、原則“なし”でも失礼にはあたらないことを強調しておきます。
ただし、以下のような場面では一時的に装着することが望ましいとされます。
- 企業の広報活動、SDGs関連の社外イベント参加時
- 来客応対や公式な社内外の式典がある場合
- ビジネス撮影(社内報・広報素材など)での見栄えが問われる場合
このような場合は、無理のない範囲で着用し、それ以外は快適性と服地の保護を優先する判断が適切です。
企業としても、ドレスコードや就業規則を「無理のない範囲」に設計することが理想的です。
女性服装での最適解
女性のビジネスウェアにおいては、服のデザインや構造に個体差が大きいため、社章やSDGsバッジの装着位置には特別な配慮が必要です。
見た目のバランス・衣服の損傷防止・留め具の安定性の3点を軸に、代表的な3パターンを整理します。
ブラウス:襟元近接やヨーク部位に小さく端正に
ブラウスは、襟が小さい・素材が薄い・ポケットがないなどの特徴があり、社章・バッジの装着には繊細な判断が求められます。
以下の点を基準に装着位置を選定するとよいでしょう。
- 襟元に近接した位置(第一ボタンから1〜2cm下、左寄り)が基本
- 襟がない場合は、肩線と前立ての交点付近(ヨークの始点)を目安とする
- 装着物は小ぶりで軽量なものを選び、着崩れやシワの原因を避ける
特に透明感や柔らかさのある素材では、社章の金属光沢が浮いて見える場合もあります。
そのため、艶消し加工や小型デザインのバッジが適しており、SDGsバッジも主張の強いものは避けた方が無難です。
ワンピース:切替線やラペル風デザインを基準点に
ワンピースには襟がない、またはデザイン的な飾り襟(フェイクラペル)が付いているものが多く、統一的な装着ガイドラインを適用しづらいのが実情です。判断基準としては以下が推奨されます。
- ウエスト上の切替線(横ライン)やダーツ縫製部位を基準とし、その上端から2〜3cm上の位置に装着
- ラペル風のデザインがある場合は、左側の折返し部(ジャケットを模した形状)をフラワーホールの代替として活用
- 素材が厚めの場合はピンタックやタイタックよりもマグネット式が推奨される
このように、「縫製のガイドライン=構造的基準線」を活用することが、見た目にも機能的にも最適な装着位置を決定する助けとなります。
アウター:厚手生地で留め具選びに注意
女性用アウター(ジャケット・カーディガン・ボレロなど)では、厚手のウール・ツイード・ジャージーなど素材の特性により、留め具の適否が大きく異なります。
- ピンタック・タイタックは生地に針穴や毛羽立ちのリスクがあるため非推奨
- マグネット式を使う場合は、磁力が強すぎると生地に圧痕が残るため注意
- ネジ式留め具は外れにくく安定感はあるものの、取り付けに手間がかかるため短時間の場面には不向き
厚手アウターの上から装着する場合は、「外からの視認性」よりも「取り外しやすさ」や「生地ダメージの抑制」を優先することが現実的です。
どっちを付ける?最終回答
社章とSDGsバッジ、両方持っている場合に「どちらを付けるべきか?」という疑問は、場面と目的によって正解が変わるため、一概に断定しにくいのが実情です。
ただし、基本原則とTPO別の最適解を整理することで、迷わず判断できる基準が得られます。
基本ルール:両方つけて問題なし
通常の勤務日やカジュアルな社内外対応であれば、社章とSDGsバッジの両方を装着することに問題はありません。
企業としての一体感(社章)と、社会的な取り組み姿勢(SDGs)を同時に示すことができるため、むしろ積極的な意思表示として好意的に受け取られます。
- 【推奨配置】社章を上、SDGsバッジをその下に
- 【注意点】バッジ間の間隔を5〜10mm程度空け、干渉や見栄えの崩れを避ける
- 【例外】大きすぎるバッジ、派手な色味の場合は調整を検討
式典や厳粛な場:社章のみが無難(弔事は主催者指示・社内規定を最優先。光り物は避ける慣行あり)
入社式、表彰式、弔事、来賓を迎える公式行事などの場では、装飾性よりも格式が重視されます。そのため、企業の正式な象徴である「社章のみ」の装着が基本とされます。
- SDGsバッジは「活動意志の表明」であり、厳密な礼装との相性が分かれる
- 社章は「身分と所属の象徴」であり、礼節を示す上で外せない要素
- 特に社外主催の式典では、SDGsバッジは省略または主催者の方針に従うのが安全
社外イベント・展示会:TPOによって判断が分かれる
展示会・採用イベント・セミナー登壇・自治体との共催イベントなどでは、「どちらを優先するか」は主催者の趣旨・自社の立ち位置によって柔軟に判断することが求められます。
| シーン | 最適な装着例 | 備考 |
|---|---|---|
| CSR・ESG関連イベント | SDGsバッジのみまたは両方 | テーマとの親和性が高く、SDGsバッジが主役になる場合も |
| BtoB展示会(業務系) | 社章のみまたは両方 | 所属の明示が重視されるため社章は原則必須 |
| 学生向け採用イベント | 両方またはSDGsバッジのみ | メッセージ性が重視され、学生にわかりやすい視覚効果を優先 |
| 物販やPRの屋外出展 | 付けない選択も可 | Tシャツ・ブルゾン等の場合はバッジが不適合なことも |
このように、「付けない選択」もTPOに沿えば正解となることを明確にしておくことで、着用者の判断の自由度を確保できます。
結論:TPOに応じて「3つの選択肢」を持つことが最適解
- 基本 → 両方つけてOK(日常業務・広報・対内イベント)
- 厳粛な式典 → 社章のみ(フォーマルな場、公式行事)
- 柔軟な社外活動 → 両方/社章のみ/付けないも可(相手軸・活動軸で判断)
バッジは単なる装飾ではなく、「どんな意思を示したいか」を表現するビジュアル・メッセージの一部です。
企業としては、社員に判断軸を提供した上で、柔軟な運用を許容する文化づくりが理想的です。
バッジが3つ以上ある場合のルール
企業活動の多様化に伴い、社員が保有するバッジの種類も増加傾向にあります。
しかし、視覚的ノイズの抑制・TPO適合・企業イメージ統一の観点から、着用点数には明確な上限ルールを設けるべきです。
運用指針:装着は2点までを推奨(社内規定があればそちらを優先)
社章・SDGs・資格証・記念バッジなど、いかなるバッジであっても、同時に装着する数は最大で2点までとするのが適切です。
- 視認性の維持:情報伝達の主目的が曖昧にならないよう整理
- 衣服のバランス:装着位置が限られており、多点付けは左右バランスが崩れる
- マナーの観点:バッジはあくまでTPO対応の一環であり、装飾とは異なる
特に対外的な場では、「何を伝えたいのか」が不明瞭になると逆効果になるため、最大2点に絞る選択が「配慮と戦略性の現れ」として好印象を与えます。
選び方:4つの判断軸
3つ以上の候補がある場合は、以下の4点を基準として装着バッジを選定します。
| 判断基準 | 説明 |
|---|---|
| ① 公式性 | 社章・社名入り徽章など、企業や身分を示すものが優先 |
| ② 伝えたいメッセージ | SDGsやCSR、記念日など、伝えたい社会的意思を反映 |
| ③ 視認性 | サイズ・色・デザインのバランスが良いものを選ぶ |
| ④ 規定順守 | 就業規則・ガイドラインがあれば、それに従うこと |
この選定プロセスを周知することで、全社的な統一感と着用者自身の納得感の両立が可能となります。
NG例:同系統バッジの多点付け
以下のような装着は、視覚的な混乱・過剰な自己主張・規律の緩みと誤認される恐れがあるため避けるべきです。
- SDGsバッジを2種以上同時に着用(例:公式カラー+企業オリジナル版)
- 記念系バッジを複数(周年記念+表彰+プロジェクト完遂など)
- 同一社章の色違いや旧版・新章の混在
これらは意図が伝わりにくく、かえって「一貫性のない印象」や「公私混同」の誤解を与える可能性があります。
結論:象徴性 × TPO適応 × メッセージ性の最適解を選ぶ
- 2点までが基本(社章+1)
- 優先順は公式性 → 社会性 → 美観性 → 社内規定
- 不要なものは無理につけず、省略も適応の一部とする
バッジは「意思を伝える装備」であり、「持っているものをすべて見せる装飾」ではありません。
絞り込みこそが、洗練された企業姿勢とされる時代において、このルール整備は非常に重要な意義を持ちます。
【比較表】留め具の種類と服地ダメージ対策
社章やSDGsバッジの装着において、見落としがちだが非常に重要な判断軸が「留め具の種類」です。
なぜなら、着用の快適性・耐久性・衣服の損傷リスクを大きく左右するからです。
実際の運用では、「どの服に、どの留め具が合うか?」を誤ると、バッジそのものの印象だけでなく、衣類や運用効率にも悪影響を及ぼします。
主な留め具4種と評価
以下に、実務で頻用される代表的な4種類の留め具を、一次情報の観点と評価軸(外れにくさ/手間/生地保護)で比較します。
| 留め具種別 | 外れにくさ | 着脱の手間 | 生地への優しさ | 特徴と注意点 |
|---|---|---|---|---|
| タイタック式 | 中 | 中 | 低 | 裏のキャッチが大きく、留めにくさを感じる場面あり。ピン穴による生地ダメージあり。 |
| ネジ式 | 高 | 高 | 中 | 外れにくさは最強だが、装着時に両手で慎重な操作が必要。裏面が硬く、生地によっては圧痕が残ることも。 |
| マグネット式 | 中 | 低 | 高 | 生地を傷めず、厚手の衣服にも対応。ただし、生地の厚みやバッジ重量次第で保持力が不足する場合がある。 |
| ピンタック式 | 低 | 低 | 低 | 装着は楽だが、構造上キャッチが緩みやすく、長期使用で外れやすくなる傾向あり。生地に穴が開くリスクも高い。 |
選定のポイント:「用途 × 生地 × 運用頻度」で判断する
装着対象やシーンによって、最適な留め具は異なります。以下のポイントで選ぶことが肝要です。
- 外れにくさ重視:人前で頻繁に動く、落下リスクが許容されない → ネジ式
- 手間を減らしたい:日常業務で毎日付け外しが発生する → マグネット式
- 衣類を守りたい:高級スーツや薄手の生地 → マグネット式、または裏あて付きタイタック
- 一時使用・軽装:記念行事やイベント等 → ピンタックも可だが、運用には注意
実務的所見
タイタックは「キャッチが大きくて不便」、ネジ式は「外れにくく安心だが手間がかかる」、マグネットは「衣類にやさしいが、重量・生地厚によってはズレやすい場合がある」—このようにそれぞれに一長一短があるため、現場ではTPOで使い分けるのが実際的。
また、ピンタックは「構造上の不安定さ」があり、長期運用にはやや不向きとの評価も重要な実地知見です。
結論:留め具は「バッジそのものの価値を左右する設計要素」
- 単なる付属品ではなく、「着け心地」「見栄え」「継続性」を決定づける要素
- 企業としては、「制服や業務内容に応じた標準留め具」を明確化し、支給時に明示しておくことが望ましい
- 特に新入社員や異動者への配布時には、「留め具の種類と扱い方」まで説明する運用マニュアルがあると理想的
清掃・保管・再装着のコツ
社章・SDGsバッジを長期間美しく、安全に運用するには、着用時以外の管理=「清掃」「保管」「再装着前チェック」が極めて重要です。特に金属・樹脂・布地などの素材はそれぞれに性質が異なり、適切なメンテナンス法も変わります。
1. 素材別:正しい清掃方法
| 素材 | 清掃方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| メッキ(金属)製 | 柔らかい布で乾拭き/汚れがある場合は中性洗剤を薄めて使用 | 研磨剤・アルコール系は厳禁(変色・剥離の原因) |
| 樹脂製(エポキシなど) | 軽い乾拭き/表面に指紋や油分がある場合は眼鏡拭きなどの超極細繊維 | 熱や溶剤に弱く、摩擦にも注意 |
| 布地・刺繍タイプ | 毛先の柔らかいブラシでホコリを除去/汚れは水拭きNG | 水分を含むと縮み・型崩れ・色移りの原因になる |
共通の基本原則:
・水洗いは原則NG(特に接着剤やピン構造が緩む可能性あり)
・ティッシュやキッチンペーパーは使用しない(繊維が残る・摩擦が強い)
・アルコール・シンナー系は原則厳禁(※メーカー推奨がある場合はそちらを最優先)
2. 正しい保管方法:袋+乾燥剤が鉄則
着用後の保管状態によって、劣化スピードに大きな差が生じます。下記を基本ルールとしてください。
- 個装袋に入れる:空気との接触を防ぎ、酸化・埃付着を防止
- 乾燥剤を添える:湿度によるメッキの曇り・変色・カビ防止(特に梅雨・冬場)
- 直射日光を避ける:色褪せ・変形・接着剤の劣化防止
- 衝撃や圧力がかからない場所に保管:他のバッジや硬質物と一緒にしない
※実務補足:長期保管用には、バッジ専用のジュエリーケースやスポンジ仕切りのある容器が理想的です。
3. 再装着前のチェック項目
再装着の際は、次の3点を毎回確認することで、不意な脱落・破損・印象低下を未然に防げます。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 緩み | ピンやネジが緩んでいないか。キャッチ部分がしっかり締まるか。 |
| 角度 | バッジの角度が水平・左右対称か(傾きは品位を下げる) |
| 艶 | 表面が曇っていないか。指紋・埃がないか(軽く磨いて整える) |
ポイント:
・出発前の鏡チェック時に「ネクタイ・名札」と並んで“バッジの3秒チェック”を習慣化することで、常に清潔で整った印象を保てます。
・社内マナー研修などでも、この確認ルーチンを共有すると、全体の印象レベルが向上します。
結論:身だしなみは“非着用時の準備”で決まる
- 清掃・保管・再装着チェックは、着けている時以上に「信頼性・清潔感・好印象」を左右する。
- これらのルールは個人任せにせず、社章やSDGsバッジの支給時に「ケアガイド」として明文化されていると理想的です。
- 特にクールビズ期間など「毎日着けない時期」がある場合、このケアがバッジ寿命を大きく左右します。
素朴な疑問:右胸にSDGsバッジはアリ?
原則:バッジ類の着用位置は「左胸」が基本
徽章(社章・SDGsバッジなど)の着用位置は、左胸が慣例的な原則です。これは日本のビジネス習慣における「名誉・信念・帰属意識を象徴する位置」として長く定着しており、特に社章のような公式な徽章は心臓に近い左胸に装着することが敬意の表れとされています。
- 社章:原則として左胸(ジャケットのフラワーホールまたはその近辺)
- SDGsバッジ:社章の下に重ねる、または場面に応じて単体で着用
この原則があるため、右胸への装着は例外扱いとなります。
例外:右胸に装着される代表例=名札・社員証
右胸は業務中に名札や社員証ホルダーが配置されるエリアとして多くの企業で定着しています。
このため、SDGsバッジを右胸に着けると視認性・識別性の観点で混乱を招く恐れがあるという点に留意が必要です。
- 名札や社員証:情報を提示する「識別アイテム」
- SDGsバッジ:信念や活動方針を表す「メッセージアイテム」
→ この2つが近接・重複することで、視認性・意味の解釈に混乱を生じる可能性があります。
判断基準:どうしても右胸に付けたい場合は?
やむを得ず右胸に装着するケースがあるとすれば、次のような配慮が必要です。
| 判断軸 | チェックポイント |
|---|---|
| 視認性 | 名札や社員証と重ならないか? |
| 意味の明確性 | 「識別」と「理念」の混同が生じないか? |
| バランス | 左右の視覚的バランスは保たれているか? |
| 社内規定 | 明文化されたドレスコードに違反していないか? |
※実務補足:社員証ホルダーの一部に社章やSDGsバッジを固定するカスタマイズ事例も存在します。この場合は「別部位への移植」と見なされ、右胸配置とは意味合いが異なります。
結論:原則左胸。右胸は社内ルール優先/識別アイテムとの混同に注意
- 原則は左胸。これは社章でもSDGsバッジでも同様
- 右胸は識別領域(名札・社員証)として確立されている
- どうしても右胸に付けたい場合は、意味の明確性・視認性・社内ルールを十分に確認することが必要
- 不安な場合は「バッジ非装着を選ぶ判断もマナー」という視点が重要
この節を図解化する場合は、下記のようなビジュアル設計が適切です:
- 左胸:社章→SDGsバッジ(縦並び)
- 右胸:名札・社員証(例示)+バッジ重複時のNG図
- 解説ラベルで「混同を避ける理由」を明記
【早見表】社章・SDGsバッジのシーン別着用ルール
| シーン | 社章 | SDGsバッジ | 備考・運用ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常勤務 | ○ | △ | 業務に支障がなければ着用OK。SDGsは任意。制服やドレスコードに従う。 |
| 来客対応 | ◎ | ○ | 社章で「所属と信頼感」を示す。SDGsは理念のアピールとして有効。 |
| 式典・表彰式 | ◎ | △ | 原則は社章のみ(弔事は主催者指示・社内規定最優先。光り物回避の慣行あり)。SDGsバッジは場により調整。 |
| 社外イベント | ○ | ◎ | 企業姿勢を示す目的でSDGs重視。社章は組織を代表する場で。 |
| オンライン会議 | △ | △ | 表示されにくいため必須ではないが、意識づけで着用も可。 |
| 軽装(クールビズ) | △ | △ | 服装・位置の制約あり。着用は無理せず場面に応じて判断。 |
- ◎=着用推奨 ○=着用可 △=着用任意(状況に応じて)
判断基準と補足解説
1. 社章の役割:組織への帰属・信頼性の可視化
- 特に来客対応や式典では、企業側の「顔」として機能するため、外さないのが基本。
- 通常勤務でも「ドレスコード上の着用義務」がある企業もある。
2. SDGsバッジの役割:理念・価値観の発信
- 社外イベントや展示会などでは、SDGsバッジが企業の取り組みを印象付ける。
- 一方で、式典や重厚な場ではややカジュアルな印象を与える可能性があり、TPOの見極めが必要。
3. 複数着用の制限とマナー
- 基本は2点まで(社章+SDGs)。
- 表示位置・留め具・衣服の形状によっては「無理に付けない」判断がむしろ好印象を与える場合もある。
結論:迷ったときは「会社の規定」と「TPO」優先
- すべてのケースにおいて、「就業規則」「ドレスコード」「職場文化」に従うのが第一。
- それでも迷う場合は、以下を基準に:
◎公式性の高い場:社章を優先
◎社会的な理念の発信が求められる場:SDGsバッジを活用
◎どちらも不要な場:無理に着用せず、自然体の整った印象を重視
一歩進んだ知識:SDGs公式図像の厳守と“自社サステナビリティ・バッジ”の設計戦略
1. SDGs公式図像と自社デザインは「明確に切り分ける」
SDGsの公式図像(ロゴ・カラー・ホイール・17アイコン)は、国際連合が著作権を保有する公共資産であり、使用には厳格なルールが定められています。
以下の行為はすべて禁止されています。
- 色や形状の変更(例:一部ゴールの色だけ強調、角型に変更など)
- 他のロゴとの統合(自社ロゴやマークとの合体)
- 商業用途・資金調達用途での無許可利用(販売促進・広告・クラウドファンディング等)
企業が自社の取り組みや価値観を可視化したい場合は、SDGs図像を使わない「自社サステナビリティ・バッジ」を独自に設計するのが安全です。
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| SDGs公式ピンバッジ | SDGsホイール(17色の円)を忠実に再現したもの | 中立的な理念の共有・国際的な信頼性 |
| 自社サステナビリティ・バッジ | 企業独自にデザイン・製造したSDGs非依存のバッジ | ブランド訴求・自社姿勢の可視化 |
※SDGs公式図像は、原則として2030年12月31日までの使用が認められています(出版物など一部例外を除く)。
2. 自社バッジに込められるメッセージと設計自由度
“自社サステナビリティ・バッジ”は、企業独自のメッセージや重点領域を、色・形状・素材などの表現手段で具体化できるのが最大の利点です。
| デザイン要素 | 表現できるメッセージ | 補足 |
|---|---|---|
| 特定色の強調 | 注力する課題領域(例:教育・環境) | ※SDGsホイールの色変更は禁止。強調表現は独自図表で。 |
| 自社理念やロゴの反映 | ブランドストーリーとの一貫性 | ※SDGs図像との統合は禁止。並置時は「支援文言」併記が必要。 |
| 金属感・透明加工など | 高級感・信頼性・実績感の演出 | 社章と同素材・同質感で整えると一体感が生まれる |
| 角型・六角形などの形状 | 革新性・業種特化・柔軟性のメタファー | ※ホイール形状の改変は禁止。自社バッジ側での表現が必須。 |
注意:SDGs公式図像は一切の加工・変形・意匠変更が禁止されています。進捗や注力ポイントは、自社設計の「独自アイコン・図表」で表現してください。
3. 社章との同時着用時に気をつけたい「調和」と「順序」
SDGsバッジは色彩豊かで視認性が高いため、社章との同時装着時には調和性・階層性・視線誘導を意識することが重要です。
配置バランス
- 左胸で縦配置する場合:社章上、SDGsバッジを下に配置するのが一般的
→ 「組織性 → 理念」の順で意味の伝達が整理される - 上下の間隔は10〜15mm程度を確保すると、視覚的なまとまりが出やすい
配色バランス
- 社章が銀・金などの金属製の場合:マット調や暗め彩度のバッジで上品さを保てる
- 濃色ジャケット(黒・紺)との相性:SDGsバッジが浮きすぎる場合は、彩度を抑えた独自設計のバッジが効果的(※公式ホイールには適用不可)
実務上の補足
- クールビズやシャツスタイル時:ピン留め位置が限定されるため、社章とSDGsバッジの両立が難しい場合もあります。→ SDGs単体での着用運用も一案です。
4. 規定に違反しないための安全運用ルール
| 規定項目 | 実務上の守るべきポイント |
|---|---|
| 改変禁止 | SDGsホイールやアイコンの色変更・形状変更・意匠追加は禁止 |
| 統合禁止 | SDGs図像と他ロゴ・社章等を一体化するデザインはNG(並置は可) |
| 支援文言の併記 | 並置する場合は「当社は持続可能な開発目標(SDGs)を支持します」の文言を必ず併記 |
| ガイドラインの明示 | 同一ページ内にガイドラインへのリンクを掲出(PDFリンクなど) |
| 商業・資金調達用途は要許可 | 販売促進・広告・収益化・商品販売等での使用は国連の事前許可とライセンス契約が必要 |
| 使用期間 | SDGs図像の使用は原則2030年12月31日まで |
本ページは情報提供を目的とし、SDGs図像の使用は国連による承認・提携・支援を意味するものではありません。
SDGs公式図像・ホイール・アイコンの使用に関しては、国際連合による公式ガイドライン(日本語版PDF) を必ずご確認ください。
よくある質問:FAQ
Q1:バッジが3つ以上あるときは、どうすればいい?
A:原則として、同時着用は2点までに留めるのが推奨されます。
目安としては「社章+SDGsバッジ」の2点が上限。
3点以上になると、視覚的な乱雑感やTPOに対する配慮不足と受け取られる可能性があります。
選び方の優先順位: 公式性・社の規定に則るもの(社章など)
伝えたいメッセージ性のあるもの(SDGsバッジなど)
視認性が高く、意味が伝わりやすいもの
▶︎ 同系統(例:複数の記念バッジ)を同時着用するのは避けましょう。
Q2:社章の代わりに社員証でも良いですか?
A:基本的には可。ただし「式典・公式の場」では社章が推奨されます。
日常勤務では、社員証ホルダーの装着で代替しても問題ありません。
実務上、クールビズ期間や軽装時には、社員証に社章を固定していた事例もあります。
ただし、以下の場面では社章が望ましいとされます: 表彰式・社内式典
取引先への訪問
採用活動・広報対応など外部露出のある場
▶︎ 企業の就業規則や慣習にもよるため、判断が難しい場合は上司や総務部門へ確認を。
Q3:留め具の種類で位置は変わりますか?
A:留め具の種類によって、着用可能な位置や安定性に差が出ます
タイタック:キャッチ部分が大きいため、スーツや厚手の生地には適応するが、つけ外しにやや不便さがある。
ネジ式:外れにくく安定性は高いが、取り付けに時間がかかる。正確な位置固定には向く。
マグネット式:衣服にダメージを与えにくい利点があるが、生地の厚みやバッジ重量により保持力不足の恐れがある。医療機器(ペースメーカー等)への配慮が必要。
ピンタック:軽量で手軽だが、構造上すぐに緩みやすく、長期間の運用には不安が残る。
▶︎ フラワーホールの有無や生地の厚さによって、適した留め具を選ぶことが位置の安定につながります。
Q4:生地を傷めにくい工夫はありますか?
A:「着用頻度・留め具選び・補強パーツ」に気を配ることで、生地ダメージを最小限にできます。
マグネット式を活用すると、生地を貫通させずに装着可能(ただし、バッジが大きすぎるとズレやすい)。
ネジ式の場合は、裏側に透明パッチや当て布を挟むと摩擦軽減に。
長期的に同じ位置に着ける場合は、あらかじめ「補強ステッチ」や「バッジ専用当て布」を仕込むと効果的。
▶︎ 定期的に装着箇所をローテーションさせることで、特定箇所のダメージ集中も防げます
まとめ:社章とSDGsバッジの使い分けと着用マナー、判断の軸を持つことが信頼感につながる
社章とSDGsバッジの使い分けは、「場面」「規定」「伝えたいメッセージ性」に応じて最適解が変わります。形式的に着けるのではなく、「なぜそれを着けるのか」という意図を持ち、TPOに即した判断を行うことが、信頼感ある身だしなみに繋がります。
着用判断の要点を振り返る
- 原則は左胸に社章を配置し、必要に応じてSDGsバッジを加える
- 同時着用は2点までが視認性・印象の観点から望ましい
- クールビズや女性服装など、衣服に応じた柔軟な運用が推奨される
- 無理に着けるのではなく、目的と場面に応じて「付けない」選択肢も適切
- 留め具・清掃・保管にも配慮することで、長くきれいに使える
判断軸をもつことで、迷わず、失礼なく、美しく
特に対外的な場面では、「自社を代表する顔」としての意識を持ち、
“どのように見せたいか”ではなく、“どう受け取られるか”を意識した配置が重要です。
- 信頼感を高めたい=社章を優先
- 理念を伝えたい=SDGsを活用
- 多すぎる装飾は逆効果=引き算の美学を意識
次の一歩へ:バッジ選びの視点にも目を向ける
この記事で装着方法とマナーを理解した上で、次は「どんなSDGsバッジを選ぶか」「どんな社章デザインがふさわしいか」といった視点にも進むと、より戦略的な印象形成が可能です。
- 公式ピン or オリジナルデザイン
- メッセージ性を持つカラー設計
- 社章との調和感を意識した組み合わせ
最後に
本記事を通じて、単なる“マナー”としてではなく、戦略的な印象形成ツールとしてのバッジ活用を考える一助となれば幸いです。
社章やバッジは、単なる装飾ではなく「静かなメッセージ」。その配置と選択こそが、企業文化や個人の品格を語る要素となります。
ぜひ貴社内のドレスコード設計や、社章・バッジの企画設計にもお役立てくださいませ。