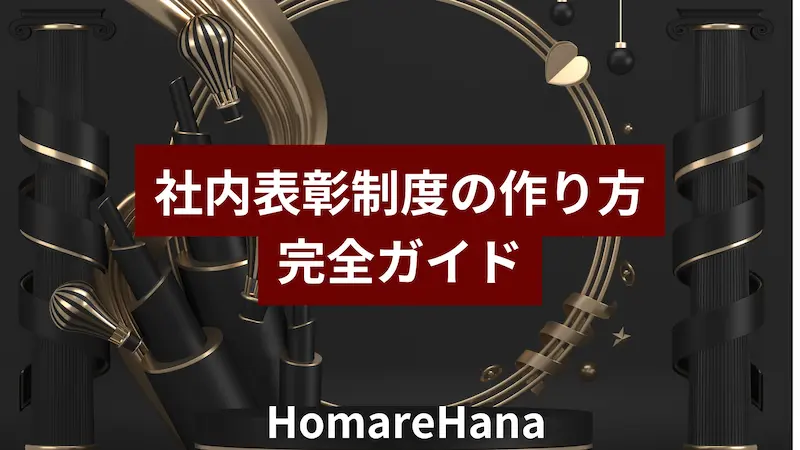
社内表彰の作り方を、基準→指標→配点→選考の順にご案内します。予算の有無にかかわらず実行できる方法なので、まずは土台から整えて小さく始め、次に広げる進め方を前提とします。
表彰の効果はKPIで厳密には測りにくいため、年1回の匿名エンゲージメント調査と表彰後アンケートで“傾向”を見て、業績の数字や現場の声と合わせて判断することを基本とします。
評価の土台は先に決めます。公平性(事前公開・測れる・同条件)、達成率、会社への貢献度を明文化し、相対評価は職種や等級ごとに分けて実施し、手順は公開して透明にします。
この記事でわかること
- 公平性・達成率・貢献度をそろえる手順
- 年1アンケートの回し方(第三者/自社)
- 表彰後アンケートの回し方
- 指標とKPIの見方(結果は“傾向”でとらえる)
- 配点モデルと選考プロセスの作り方
- 例外の扱い(回答不足・小規模部署・同点時)
本ページは制度設計の実務ガイドです。制度の目的・メリットとデメリット・税務や副賞などの全体像は上位ページで整理しています → 社内表彰とは。さらに、社内に限らない表彰の種類・式典準備・表彰品選定といった基礎は、総合ガイドご覧ください → 表彰とは。

この記事の監修・執筆は誉花編集部
本記事は、徽章・表彰分野で10年以上の実務経験をもち、経営・企画・マーケティング・AIを活用した業務効率化、社内イベント運用の経験をしている誉花編集部が監修・執筆しています。
1分で理解できる全体像

- 基準を決める
- 指標(KPI)を選ぶ
- 配点を決める
- 選考の手順を決める
効果の把握は、年1回の匿名エンゲージメント調査で全社の流れを俯瞰し、表彰後の短いアンケートで受け止め方を確認して、数字と声の両面から“傾向”として読み解きます。
このページは実務でそのまま使える形で要点を並べているので、自社の状況に合わせて必要な部分だけを選び、できるところからすぐ実行へ移していただけます。
社内表彰の目的定義
社内表彰制度の目的は、自社の戦略に沿って定義することが大切です。ただし、戦略だけを優先すると、数字が出やすい部署や職種ばかりが有利になる危険があります。そのため、目的の設定段階で「公平性を保つ仕組み」も同時に設計する必要があります。
これは、企業には成果が分かりやすく評価されやすい部署や職種がある一方で、成果が見えにくかったり、アピールが苦手で正当に認知されにくい部署や職種も存在するためです。
まず、経営陣・部門長・人事が同じ場で、事業戦略や年度計画の中から“全社で伸ばしたい成果”と“文化として根づかせたい行動”を議論します。このとき、次の3つの視点を必ず含めます。
- 戦略との整合性:戦略KGIやKPIと直接つながるかどうか
- 部門間の公平性:部署や職種ごとの指標難易度や貢献形態の違いを吸収できるか
- 測定可能性:社内で安定して集計できるデータ源があるか
この議論を経て、目的は大きく2種類に整理します。
- 業績を伸ばすこと 売上や利益、品質、顧客満足(CS)など、会社の数字に直結する成果。 例:売上増加、利益率改善、納期遵守率向上、CSスコア向上。
- 行動と価値観を広げること 長期的な競争力を高める行動や文化。 例:挑戦、協力、改善、安全、誠実、ナレッジ共有。
目的と指標のひもづけ(汎用例)
目的ごとに、部門特性を考慮した上で測れる形に落とし込みます。下記は例です。
- 売上を伸ばす → 月次売上、粗利率、新規案件数(営業・マーケティング部門向け)
- 品質を高める → 不具合率、納期遵守率、再作業時間(製造・開発・品質管理部門向け)
- 協力を広げる → 複部署プロジェクト参加数、支援件数、メンタリング回数(全社共通)
- 改善を増やす → 改善提案数、採用率、効果額または影響度(事務・オペレーション部門も含め適用可能)
このように、事業戦略から落とし込む目的と、部門特性を加味した公平性の仕組みを同時に設計することで、「戦略への貢献」と「全社員が参加できる仕組み」の両立が可能になります。
部門別のKPI例
下記は一般的なKPI例です。
| 部門 | KPI(定量) | KPI(定性・行動) | データ源 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 経営企画 | 予算差異の縮小率/全社KPI達成率/コスト最適化額 | 全社プロジェクトの推進度/意思決定の準備品質 | 予算実績、OKR、PJ管理 | 外部要因のぶれは四半期平均で見る |
| 企画(事業・プロダクト) | 新企画採用率/PoC成功数/リリース期日遵守率/機能利用率 | 顧客課題の深掘り回数/検証ログの充実度 | 企画審議ログ、開発チケット | 早期指数と事後指数を分けて評価 |
| マーケティング | MQL数/SQL化率/創出額/CVR/CAC | 顧客理解の共有回数/ナレッジ提供 | MA、CRM、アナリティクス | リードの質は営業合意の定義で固定 |
| 営業(B2B) | 受注件数/受注率/粗利額/平均契約額/サイクル日数 | 予実の精度/案件レビューの実施 | CRM、見積、受注台帳 | 価格要因は粗利で補正して比較 |
| 人事 | 採用充足率/採用リードタイム/定着率/研修受講率 | 面接フィードバックの品質/オンボ支援 | ATS、人事DB、LMS | 定着率は入社後6・12か月で確認 |
| 情報システム | システム稼働率/インシデント件数/SLA達成率 | 変更管理遵守/改善提案採用数 | ITSM、監視、変更申請 | 重大度で重み付け |
| 財務・経理 | 月次早期化日数/決算差異件数/請求誤り率 | 監査指摘の是正スピード | 仕訳、決算、監査記録 | 繁忙期は前年同月比で補正 |
| 製造(生産) | 稼働率/OEE/不良率/歩留まり/タクト達成率 | 5S実行度/標準作業遵守 | 生産実績、MES、品質記録 | 段取り替え時間は別指標で管理 |
| 品質保証・品質管理 | 不良率/クレーム率/是正処置完了率 | 品質監査実施度/再発防止の定着 | 品質管理表、監査記録 | 市場クレームは四半期で評価 |
| 購買・調達 | 調達単価改善額/納期遵守率/在庫回転日数 | 代替調達の確保/サプライヤ監査実施 | 購買台帳、在庫 | 為替影響は別途注記 |
などがあります。企業によって違いますので、一度洗い出してみてください。
社内表彰の配点と重み付けの設計
社内表彰制度の効果を最大化するためには、目的や指標だけでなく、配点と重み付けの設計が欠かせません。ここでの設計が制度の信頼性と納得感を左右します。
配点設計の基本方針
配点は、全社戦略と部門特性の両方を反映させる必要があります。これにより、戦略への寄与度と公平性を同時に確保できます。
戦略寄与の大きさ
全社や部門の戦略に直結する指標ほど配点を高くします。例えば、新規事業立ち上げ期であれば、新規案件数やパイロット成功率など、直接的な成果指標の比重を高く設定します。
達成難易度と部門特性
部門ごとの役割や成果の出やすさに応じて配点を補正します。営業と製造では指標の性質が異なるため、同一基準では不公平になりやすいです。
全社で共通する配点構造の例
配点構造は全社で共通の骨組みを持たせつつ、部門ごとに細かく調整します。
- 業績指標(売上、利益、品質など):50〜60%
- 行動・文化指標(協力、改善、価値観など):30〜40%
- 特別枠(部門固有の戦略指標や臨時プロジェクト貢献など):10%前後
この構造にすることで、全社共通の評価基準と部門固有の特色を両立できます。
公平性を担保するための工夫
公平な評価のためには、指標や評価方法を部門特性に合わせて調整することが重要です。
- 同じ指標でも部門ごとに基準値を設定する
例:製造の不良率基準と営業の成約率基準は別にする - 結果だけでなく過程も評価する指標を入れる
例:案件数だけでなく提案活動数も評価対象にする - 達成率をパーセンテージで評価し、絶対値の差がそのまま格差にならないようにする
こうした工夫により、戦略への貢献と部門間の公平性を両立できます。
選考プロセスの設計
社内表彰制度の信頼性を高めるためには、選考プロセスを明確化し、誰が見ても理解できる形で運用することが重要です。
選考の基本フロー
選考プロセスは、推薦から最終承認までの流れを整理し、全社員が確認できる状態にしておきます。
- 推薦受付(自己推薦、他薦、上司推薦など方法を明記)
- 一次採点(各指標に基づく定量評価)
- 二次審査(委員会による定性評価やヒアリング)
- 最終承認(経営層または委員会議長による決定)
- 社内発表と通知(受賞理由を含めて公開)
この流れを明文化することで、選考の透明性が高まり、不満や誤解を減らすことができます。
推薦の方法と基準
推薦の段階で基準やフォーマットを統一することで、選考の公平性が保たれます。
- 推薦フォームや推薦書の書式を統一する
- 推薦理由は具体的なエピソードと指標に沿って記載する
- 部門間の推薦数に偏りが出ないよう制限や調整を行う
こうすることで、推薦内容の質が安定し、後の採点や審査がスムーズになります。
審査の透明性を高める方法
審査段階での不透明さをなくすため、評価基準や結果の共有方法もあらかじめ決めておきます。
- 評価基準は事前に全社員へ公開する
- 採点表や議事録は委員会内で保管し、必要に応じて開示できる状態にする
- 受賞理由は社内発表時に具体的に説明する
こうした取り組みにより、審査への信頼感が高まり、制度の継続性も確保されます。
このように選考プロセスを明確化し、手順と基準を全社員と共有することで、表彰制度は透明性と納得感を持って運用できます。頼感と制度の継続性が高まります。
なお、表彰制度を一時的な取り組みではなく、恒常的な社内制度として位置づける場合は、就業規則への明記が必要となることがあります。
特に、表彰に伴い金銭報奨、物品支給、特別休暇付与などの待遇上の取扱いが発生する場合は、就業規則の「表彰」に関する条項として、対象者の範囲、選考基準、手続き、報奨内容および支給時期を具体的に規定します。
規定変更の際は、労働基準法に基づき、過半数代表者への意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です。これにより、制度運用の法的有効性を確保するとともに、社員への説明責任と待遇面での公平性を担保できます。
公平にする工夫

評価の透明性と納得感を高めるためには、先入観を排除し、ルールを事前に共有し、意見を吸い上げて改善する仕組みを持つことが重要です。
名前を隠して採点/複数人で見る
採点時に先入観をなくすため、候補者名や部署名を外し、評価は必ず複数人で行います。
- 候補者名や部署名を採点シートから外す
- 評価は複数人で実施し、平均化して最終スコアを算出
- 必要な場合も役職や顔写真など先入観につながる情報は除く
この方法により、個人や部署への好悪感が評価結果に影響する可能性を最小限に抑えられます。
公開する項目(基準・配点・手順・日程)
制度運用の透明性を高めるため、評価基準や配点、選考手順、日程を事前に全社員へ公開します。
| 公開項目 | 内容例 | 公開目的 |
|---|---|---|
| 評価基準 | 売上増加、品質改善、チーム貢献など | 評価対象を明確化する |
| 配点構造 | 業績50%、行動30%、特別枠20%など | 重み付けの透明性を確保 |
| 選考手順 | 推薦→一次採点→二次審査→最終承認 | 流れの理解と納得感の向上 |
| 日程 | 推薦締切日、選考日、発表日 | スケジュールの周知と混乱防止 |
この情報を公開することで、評価されるポイントと進行状況を全員が把握でき、不信感や不公平感を防げます。
意見を吸い上げて次回に反映する仕組み
選考結果に関する感情的な不満ではなく、制度改善につながる意見を拾い上げる仕組みを設けます。
- 表彰発表後にアンケートを実施
- 評価基準や手順の理解度、納得度を質問
- 自由記述で改善案や気づきを収集
- 回答は匿名で集計し、次回の制度設計時に反映
こうすることで、現場の声を制度改善に生かしつつ、選考プロセス全体への信頼性を高められます。
表彰後のアンケートとエンゲージメント調査
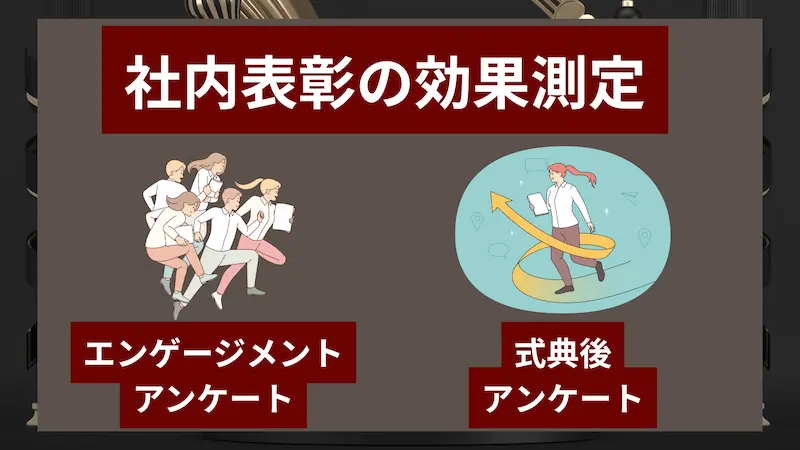
社内表彰制度の効果を把握するためには、表彰の直後と年1回のエンゲージメント調査を組み合わせる方法が有効です。これにより、制度が社員の意欲や組織の一体感にどの程度影響しているかを把握できます。
表彰後アンケートの目的と内容
表彰直後にアンケートを実施することで、社員が表彰をどう受け止めたか、制度がモチベーションに与えた影響を把握できます。
- 表彰の納得感(評価基準や選考過程への理解度)
- モチベーションの変化(表彰後にやる気が上がったか)
- 今後の改善点(制度や運用に関する意見)
このアンケート結果は、制度改善の短期的な指針になります。
年1回のエンゲージメント調査
長期的な傾向をつかむためには、全社員対象のエンゲージメント調査を年1回実施します。予算の有無によって方法を変えます。
- 予算がある場合は、第三者機関による匿名調査を依頼し、専門的な分析レポートを受け取る
- 予算がない場合は、自社でしっかりとした設問を作成し、匿名で全社員に実施する
この調査により、制度の効果や組織の状態を中長期的に把握できます。
質問項目作成のポイント
効果的な質問を作るには、モチベーションや組織文化に直結する項目を入れることが重要です。
- 会社の方針や目標に共感できているか
- 自分の貢献が正当に評価されていると感じるか
- 同僚や上司との信頼関係があるか
- 表彰制度が自分のやる気に影響を与えているか
適切な質問項目を設定することで、調査結果が制度改善の具体的な根拠になります。
このように、短期的な反応を把握する「表彰後アンケート」と、長期的な傾向を測る「年1回のエンゲージメント調査」を組み合わせることで、制度の効果を数値や傾向として把握できます。
無料で使えるアンケート質問集のご案内
この記事で紹介した「表彰後アンケート」と「年1エンゲージメント調査」の質問例を、そのまま使える資料としてご用意しました。予算がない場合でもすぐに運用を始められます。
社内エンゲージメントアンケート質問集(Word形式)ダウンロードする
式典後のイベント改善アンケート質問集(Word形式)ダウンロードする
実体験からの学び(4社での気づき)
| 会社 | 表彰の特徴 | 実態 | 透明性 | 対象範囲 | 社員への還元 | 問題点 | 成功要因 | 学び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1社目:東証プライム上場 | 不定期、基準非公開 | 同じ人ばかり受賞 | 低い | 営業中心 | インセンあり(偏り) | 受賞者が固定化、基準不明 | なし | 基準明確化と対象拡大が必要 |
| 2社目:同族系中小 | 社長独断 | 公平性ゼロ | 極低 | 恣意的 | 還元なし | 基準なし、透明性なし、形だけ | なし | 透明性と実利還元が必須 |
| 3社目:中堅ハウスメーカー | 営業上位表彰傾向 | 非営業の受賞少ない | 中 | 営業偏重 | 表彰状のみ | 部門間の不満、対象偏り | なし | 全社員対象の仕組みが必要 |
| 4社目:東証プライムITグループ | 明確基準+定性・定量評価+全社投票 | 全社員が参加意欲を持ち信頼度向上 | 高い | 全社・多部門 | 評価や称賛が広く行き渡る | 特筆すべき大きな問題なし | 基準明確、多面的評価、公平運用、改善継続 | 透明性・多様性・改善で制度が文化として定着 |
4社で社内表彰制度のある職場を経験し、その中で制度がうまく機能している会社と形だけで終わっている会社の差を強く感じました。経験的にも理論的にも、制度そのものより運用の質や透明性が成果を左右しやすいと思います。
1社目:東証プライム上場企業・営業部中心の不定期表彰
営業部で不定期に表彰が行われ、表彰状とインセンティブが授与されていました。しかし受賞者はほぼ固定で、売上上位の同じメンバーばかり。努力しても選ばれない社員が多く、表彰は一部の人のための儀式になっていました。
- 失敗していたポイント:評価基準が公開されず、受賞者が固定化。努力と評価が結びつかない状態が続き、モチベーションの広がりがなかった。
- 得られる教訓:基準の明確化と評価対象の多様化は、制度が形骸化しにくくなると思う。
2社目:オーナー経営の中小企業・社長の独断による形だけの式典
40年以上の歴史を持つ同族経営の中小企業でしたが、社内に公式な評価制度や表彰制度はなし。評価は社長の独断で行われ、公平性は皆無。所属した最後の年には全社員を対象にした表彰イベントが行われましたが、賞金はなく、贈られたはずのトロフィーも社員に渡らず社長室に飾られました。低成績な人と好成績な人両方が離職していく傾向がありました。
- 失敗していたポイント:評価基準・手順・目的が存在せず、称賛がトップの自己満足に終わっていた。
- 得られる教訓:透明性と社員への還元がない表彰は、信頼を損ないやすいと思う。
3社目:中堅ハウスメーカー・営業偏重の表彰
営業成績上位者を表彰し、表彰状を授与する制度。ホスピタリティ賞もありましたが、実際には営業職以外の受賞はほとんどなし。非営業部門からは「また営業だけ」と不満が漏れ、参加意欲は低下していました。離職率がとても高かったです。
- 失敗していたポイント:評価対象が限定的で、部門間の公平性が欠けていた。
- 得られる教訓:全社員が評価対象になる仕組みを作る方が、制度が分断を生みにくいと思う。
4社目:東証プライムIT企業グループ・明確な基準と多面的評価
親会社の文化をベースに、経営計画に基づき、全社・部門・個人の目標を設定。個人KPI達成率を絶対評価で確認し、その後に相対評価と役員・人事・コーポレート部門による議論を経て受賞者を決定していました。業績だけでなく、顕著な定性的貢献や職場の雰囲気を良くするホスピタリティも評価対象に含まれ、一部の賞では全社員による投票制も採用。さらに、エンゲージメント調査や表彰後のアンケートを通じて改善を重ね、制度が現場に適応していました。離職率も低く業績も右肩上がりで安定的。
- 成功していたポイント:基準の明確化、定性・定量のバランス、複数部門による合議、一部全社員投票の併用、改善サイクルの確立。
- 得られる教訓:透明性・多様性・継続的改善が揃うと、制度が文化として根づきやすいと思う。
よくある質問:FAQ
このFAQは、社員表彰を「基準→指標→配点→選考」で設計・運用する際の判断基準を統一するためのものです。
Q1:なぜKPIだけで効果を測らないのですか?
A:社員表彰の効果は、数字だけでは正確に把握しにくいためです。
・モチベーションや文化の変化は数値化しづらく、反映まで時間がかかる
・外部要因で数字が変動する可能性がある
・社員の納得感や反応も重要な判断材料になる
そのため、KPIとあわせて「年1回の匿名エンゲージメント調査」と「表彰後アンケート」で“傾向”を把握します。
Q2:予算がなくても実施できますか?
A:可能です。金銭や物品がなくても、社員の承認欲求を満たすことで十分な効果が期待できる可能性があります。
・基準・配点・選考手順・日程を事前に公開し、評価ポイントを明確にする
・表彰状や社内発表で成果と行動を社内に広く共有する
・推薦理由や受賞理由を具体的に伝え、本人の貢献を可視化する
表彰の本質「正当に評価され、組織から承認されること」にあります。インセンティブなどは重要ですが、費用よりも、この心理的満足をどう設計するかが重要です。
Q3:公平性はどのように担保しますか?
A:評価の透明性と先入観の排除が重要です。
・候補者名や部署名を非表示にして採点する(ブラインド評価)
・複数人で採点し、平均化する
・職種や等級ごとに相対評価を行う
・評価基準や手順を事前に全社員へ公開する
Q4:部門ごとの指標はどう選びますか?
A:本文で示した3つの視点を基準に選びます。
・戦略との整合性:会社のKGIや重点KPIと直接つながるか
・部門間の公平性:職種ごとの難易度や貢献形態の違いを吸収できるか
・測定可能性:安定して集計できるデータ源があるか
この3点を満たすことで、比較可能で公平な指標設計が可能になります。
Q5:配点比率は固定ですか?
A:基本構造は共通化し、事業環境に合わせて年次で見直します。
下記は一例です。
・業績指標50〜60%
・行動・文化指標30〜40%
・特別枠10%前後
事業フェーズに応じて特別枠の割合を調整し、変更時は必ず事前に全社員へ告知します。
Q6:小規模部署やデータ不足はどう対応しますか?
A:評価の信頼性を確保するため、例外ルールを事前に定義します。
・一定のデータ量に満たない場合は上位単位で評価する
・定量評価が難しい場合は定性評価を限定的に補強する
・評価期間を延長してデータ量を確保する
Q7:同点の場合はどう決定しますか?
A:本文で推奨しているタイブレーク基準を用います。
・会社全体への影響度
・必要に応じて同時受賞や特別表彰とする
Q8:個人表彰とチーム表彰はどう区別しますか?
A:目的と評価軸を分けて設計します。
・個人:成果や行動を可視化し、ロールモデルを示す
・チーム:協働からの成果や仕組みづくりを評価し、文化を広げる
・配点や評価基準は別建てにすることで混同を防ぎます
Q9:不正や数値の作為はどう防ぎますか?
A:公式データと監査で健全性を維持します。
・公式な記録だけを採点に使用する
・異常値は確認・検証する
・管理者の承認フローを設ける
・故意の不正は表彰対象外とする
Q10:自社でエンゲージメント調査を行う際の注意点は?
A:匿名性と比較可能性を確保します。
・設問は方針共感、公平感、信頼関係、表彰の影響を含める
・5段階評価と自由記述を併用する
・少人数の結果は非開示にする
・調査結果と改善策を全社員に共有する
まとめ
社内表彰は「基準→指標→配点→選考」を土台に、公平性と戦略整合性を両立させて小さく始め、データと現場の声で継続的に改善する運用が要点です。厳密なKPI一本足ではなく、年1回の匿名エンゲージメント調査と表彰後アンケートで“傾向”をとらえ、数値と定性を組み合わせて意思決定します。
- 公平性の確保:事前公開・測定可能・同条件を明文化し、相対評価は職種や等級ごとに分離して透明に運用します。
- 目的と指標:戦略的成果(業績)と文化的行動(価値観)を二本立てにし、部門特性に合うKPIへ落とし込みます。
- 配点モデル:業績50〜60%/行動30〜40%/特別枠約10%などを基準に、達成難易度・役割差で重み付けを補正します。
- 選考プロセス:推薦→一次採点(定量)→二次審査(定性・ヒアリング)→最終承認→社内発表を明文化し、ブラインド評価・複数採点者で先入観を抑制します。
- 透明性の運用:基準・配点・手順・日程を全社員へ公開し、記録を保全。例外(小規模部署・同点・回答不足)も事前に扱いを定義します。
- 効果検証:表彰直後の短いアンケートで短期反応を、年1回の匿名調査で中長期の流れを把握し、改善サイクルに反映します。
- 制度の定着:金銭・物品・特別休暇など待遇を伴う場合は就業規則に条文化し、所要の手続きを踏んで法的有効性と説明責任を担保します。
- 実践知の教訓:不透明・偏重・独断は制度を形骸化させ、明確基準・多面的評価・全社員参加と継続改善が信頼と成果を高めます。
以上を満たせば、予算の有無にかかわらず再現性の高い仕組みになります。まずは公開可能な最小セットで運用を開始し、検証→改善で段階的に広げていくことをおすすめします。